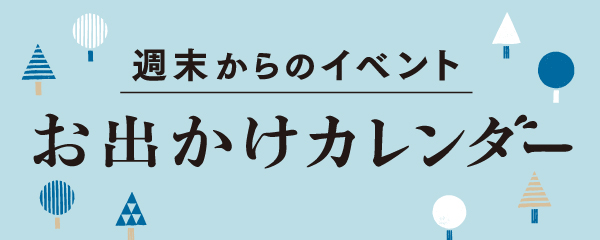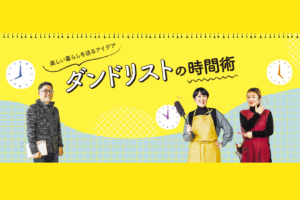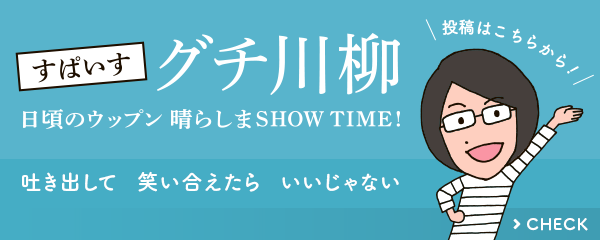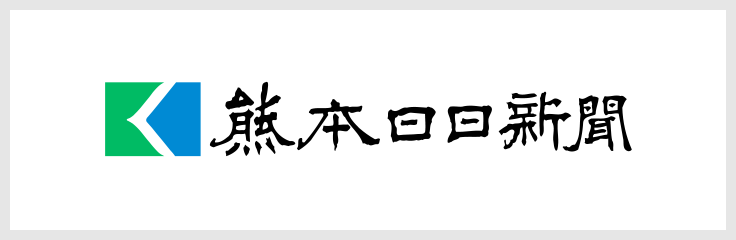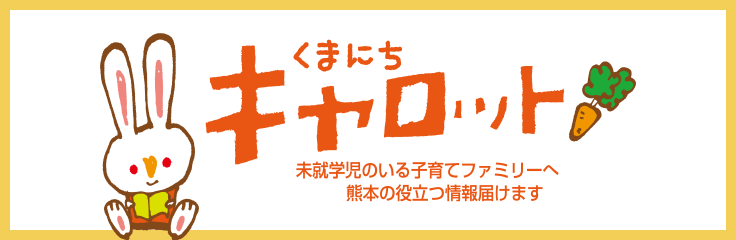【セカンドライフ熊本2025】デジタル終活

「セカンドライフを心豊かに過ごしたい」。そんな意欲的な人たちと、その子ども世代に向けて、今を楽しむコツと未来に備える方法をテーマごとにお伝えします。
もしもに備えて知っておこう デジタル終活
オンライン決済が当たり前の時代。親族が亡くなった際、ネット上にある資産や各種サービスの情報にアクセスできずに困ったというトラブルがあるようです。そのようなデジタル遺産と向き合う終活について、ファイナンシャルプランナーの広瀬美貴子さんに聞きました。
オンライン契約やデジタル資産 まずはリストにして「見える化」
最近は、年配の方でもスマホで買い物をしたり、ネット銀行を使ったりと、日常生活でデジタルサービスを利用する機会が増えています。そうした情報を本人しか把握していないと、死亡後に家族が手続きできずに困ることに。ファイナンシャルプランナーの広瀬美貴子さんは「相続では不動産や預貯金など“見える遺産”でさえ手続きが煩雑で、家族には負担になります。ましてやどこにあるか分かりにくい“デジタル資産”は、さらに対応が難しく、放置されるケースが増えているようです」。
対策は、契約内容を整理し一覧にして“見える化”しておくこと。銀行、証券、保険、公共料金の引き落とし先、契約しているサブスクリプション(定額料金サービス)などを書き残しておくだけでも、家族には大きな手掛かりになります。IDやパスワードの取り扱いにも工夫を。ログインやパスワードの情報を保管している場所だけ伝えておいたり、修正テープでパスワード情報を隠し、必要なときにコインで削って確認してもらったりする工夫もおすすめだそうです。
「デジタル終活は、家族が困らないための思いやりです。お盆や正月など家族が集まる機会に、契約や資産の整理について話し合う機会を持ってみてください」と広瀬さん。まずはデジタル資産のリスト化から始めてみましょう。
教えてくれた人
デジタル資産を”見える化”することから始めましょう


広瀬 美貴子さん
残す側のポイント【親世代】
スマホにログインできるよう準備
デジタル終活と聞くと難しく感じるかもしれませんが、残された人がスマホやパソコンにログインできるよう準備をしておくことから始めましょう。これだけでも、重要な情報にアクセスしやすくなります。IDとパスワードは別管理が原則。自分が亡くなった後に家族が必ず見る物や場所を想像し、別々に忍ばせて保管しておくなどの方法があります。
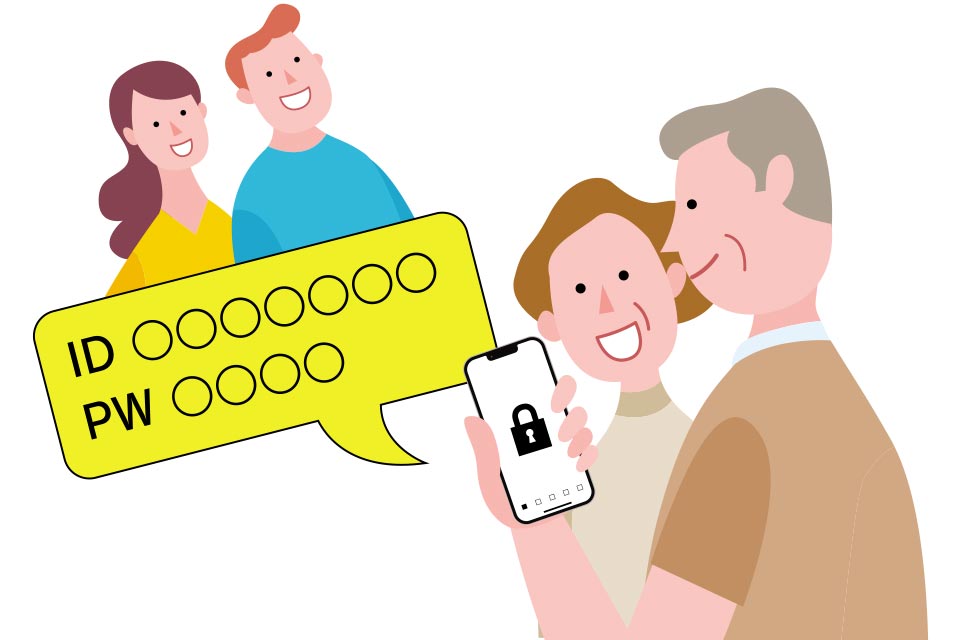
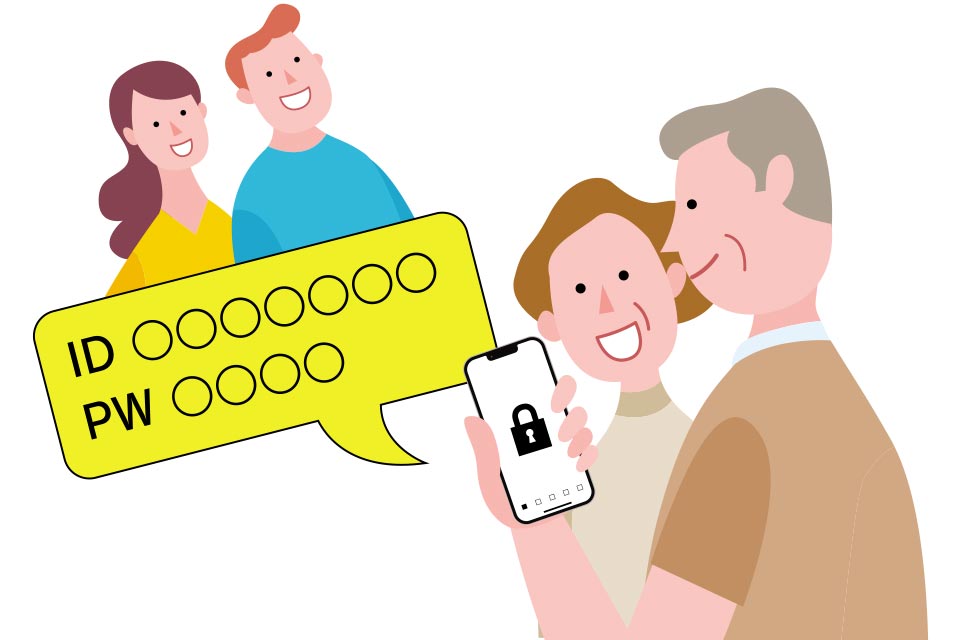
残す側のポイント【子世代】
死亡書類で解決の場合も
ネット銀行や証券、保険、サブスクなどの契約は、ログイン情報が分からないと手続きが滞ることがあります。どこと契約しているかが分かっている場合は、死亡届の写しなど必要な書類を提出することで、解約や払い戻しに応じてもらえることがあります。使っていたサービス自体が分からない場合は、クレジットカードの明細やメールの履歴が手がかりになることも。ただこれらの方法での対応には時間がかかるため、日頃から情報を共有しておくことが大切でしょう。