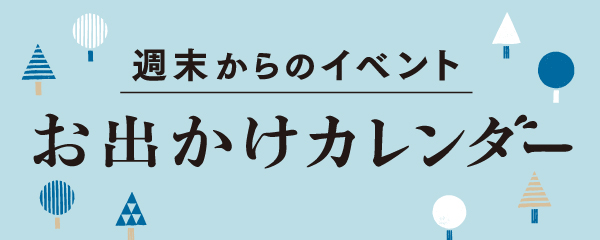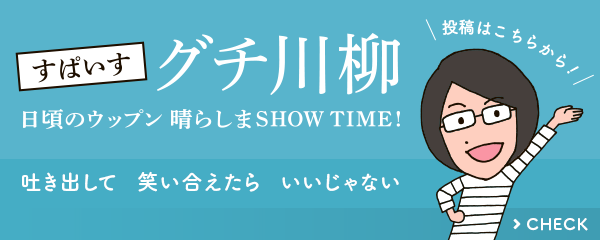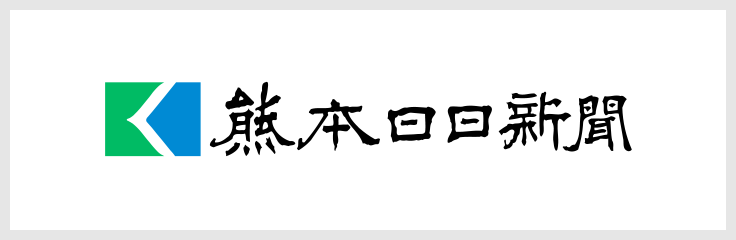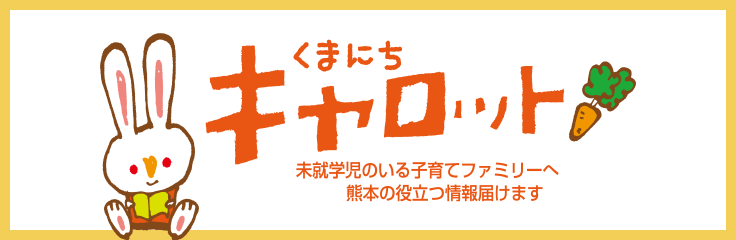はかなさを大切にする縄文時代

世界遺産に登録されている函館市の垣ノ島遺跡に行ってきました。函館市縄文文化交流センターには、南茅部地区の著保内野(ちょぼないの)遺跡で発掘された「中空(ちゅうくう)土偶」が展示されていました。
中空土偶は中が空洞で、国宝に指定されている同センター展示の中空土偶は国内最大のもの。元館長の阿部さんは「両腕と頭部の飾りが欠損しているこの土偶をCTスキャンしたところ、割れないように内面を調整した箇所と調整していない箇所があったんです。つまり最初から壊れるという前提で、都合のいい部位で壊れるように作られていたのではないでしょうか。頭が真ん中から割れたりしないような工夫です」と教えてくださいました。
また、9000年前の漆の技術で作られている赤漆塗りの注口土器は外側が赤、内側は黒で、黒は「死」を赤は「血(生)」を表現しているそうです。
私の心が一番動いたのは「貝塚」の話。ここの貝塚からは食べかすだけでなく、人骨や犬の骨、壊れた土器や石器なども出土していて、単なるごみ捨て場ではなく、命が終わったものを大切にあの世に送り、再びこの世に戻ってくることを願う儀式的な場所だったのではと考えられているそう。
縄文時代早期9000年前から3000年前までの6000年という長い間、自然の一員として生きていた縄文の人々の暮らしは、「生と死の命の循環」と「はかなさを大切にする想い」に満ちていました。