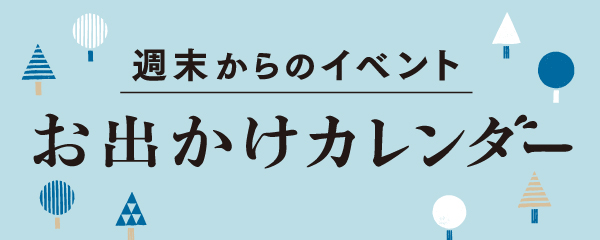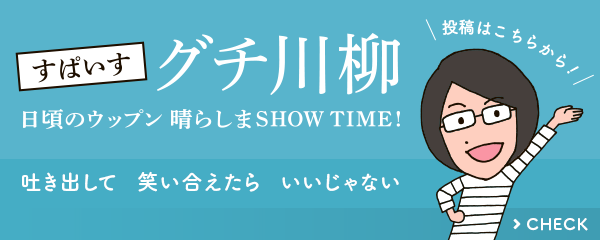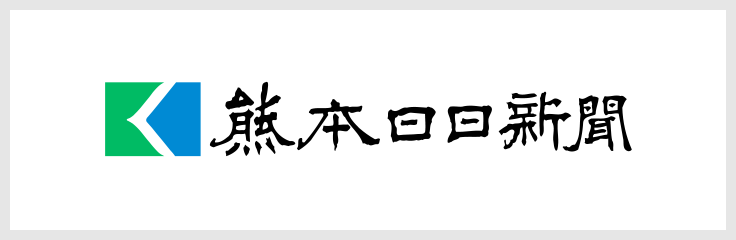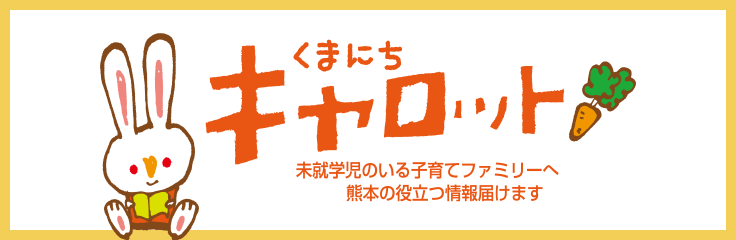進路選択へ 多様化する大学の学部、学科 早めに情報収集を
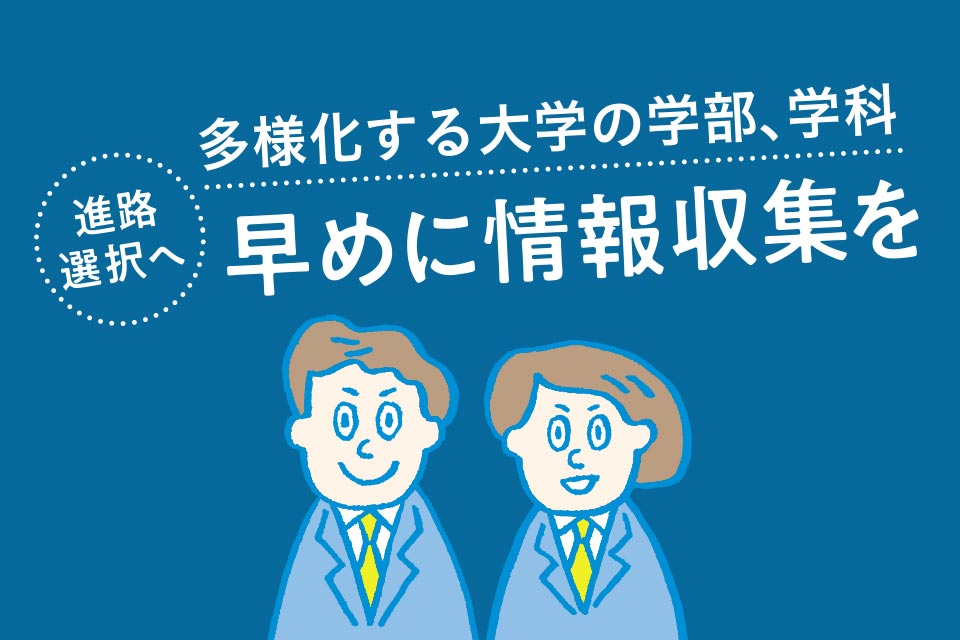
近年、全国の大学で学部・学科の再編や新設の動きが活発化しています。それは熊本も例外ではありません。情報を敏感にキャッチして、受験に備えるようにしましょう。
半導体企業進出を機に 県内大学の再編が加速
大学では全国的に学びの多様化が進んでいますが、県内では台湾積体電路製造(TSMC)の進出をきっかけに、特に半導体関連の学部や学科の新設が顕著です。他にも文系と理系を統合した学部を設けたり、海外の姉妹校と連携を深めたりする大学も増えています。
熊本大は2024年度にデータサイエンスや半導体を学ぶ「情報融合学環」をスタートさせ、26年度には経営学を含む文理融合の「共創学環」を新設。県立大では、「半導体学部(仮称)」を27年春に開設する予定です。私立大でも、スポーツ振興に力を入れたり、産学連携の拠点を設立したりするなど個性的な取り組みが広がっています。
大学卒業後の進路についても、これまで身近ではなかったような職種や分野に進むことも可能になってきました。将来を見据えて新しい情報を仕入れて、大学選択や受験対策に生かしましょう。
大学受験の対策は高校1年から始めよう
大学受験への取り組みは、高校1年のうちから始めることが大切です。
ほとんどの高校で、高1の後半か2年進級時に「文系クラス」「理系クラス」を選択します。科目の得意不得意を基準に選ぶのも一つの方法ですが、ここで選択を誤ると後で軌道修正が難しくなってしまいます。文理選択は慎重に行いましょう。
1、2年時は、進路が定まっていないと勉強に身が入りにくいものです。塾関係者は、「そういった生徒は、苦手科目を中心に勉強するといい」と助言します。苦手科目をなくしておくと、大学受験の時に有利に働きます。高2になったら、大学のオープンキャンパスなどに参加して気持ちを固めましょう。
近年、大学入試制度は多様化しています。国公立も「大学入学共通テストと個別(二次)試験」だけでなく、総合型選抜、学校推薦型選抜などさまざまです。まずは自分が行きたい大学の入試制度を調べておきましょう。志望大学を早めに決めれば、受験対策も早めに始められます。


同一の期日で実施される全国共通のテスト。問題の作成、採点などは独立行政法人大学入試センターが運営。2026年度入試は、26年1月17・18日に行われる。
高校3年間の成績や校内外での取り組み、活動のほか、小論文、面接などを総合的に評価して合否を判断する。大学や学部によって選抜方法は異なる。
高校からの推薦を受けることで出願できる入試制度。一般的に、指定校推薦の場合は各校1人〜数人の枠があり、推薦を受けるには一定以上の成績が求められる。入試では書類審査のほか、小論文や面接、独自の学科試験が実施される場合がある。
高校入学から大学受験までの流れ
1年
- 入学
文系・理系クラス分け
2年
- 進学情報収集
大学選択
3年
4月〜12月
- 高校総体、高校総文祭
- 総合型選抜試験
- 学校推薦型選抜試験
冬休み
1月〜2月
- 大学入学共通テスト
- 私立一般入試
2月〜3月
- 国公立大個別(二次)試験
- 前期日程(2月末ごろ)
- 後期日程(3月中旬ごろ)
※試験の日程等は一般的なスケジュールを大まかに反映させたもので、高校、大学によって異なります


Q&A
- 大学の受験勉強は総体後からでも大丈夫?
高校では部活動を頑張っています。勉強との両立が難しく、今は少し成績が停滞気味です。大学の受験勉強は、高校総体が終わってからでも間に合いますか? -
高校総体が終わると、他の生徒も一斉に勉強に集中し始めるため、そこから成績を上げるのは難しくなります。1、2年のうちに学習習慣を身に付けて、苦手科目を克服することが大切です。定期テストを頑張っておくと、学校推薦を取りやすくなり、進路の選択肢も広がります。


熊本ゼミナール 運営部 部次長 宮川史比古さん - 医療系に進みたいけど選択肢が多くて迷います
医療系の大学か専門学校への進学を希望しています。ただ、医療系は県内外に数多くあって決めかねています。何を基準に選んだらよいでしょうか。 -
「医療系」と一口に言っても、医師や看護師、助産師、診療放射線技師など職種はさまざまです。「どんな仕事に就きたいのか」までを考えて、進学先を選びましょう。せっかく大学に合格しても、なりたかった助産師の資格は取れない…なんてことにならないよう気をつけて。将来像を明確に持つようにしましょう。


熊本ゼミナール 個別指導部 ブロック長 寺岡佑造さん