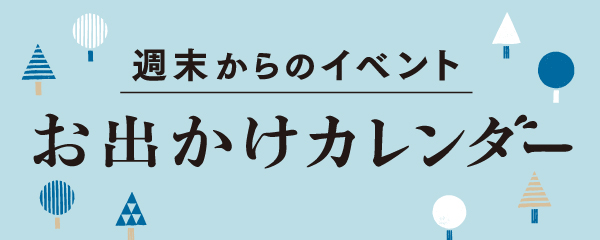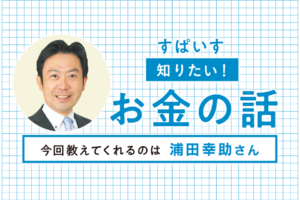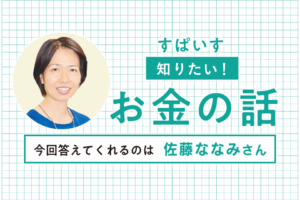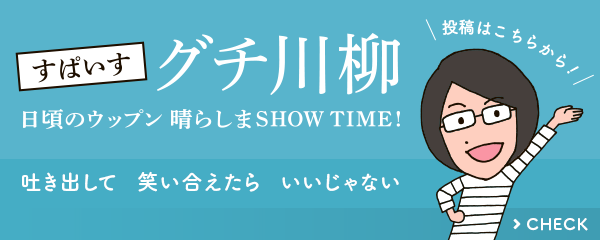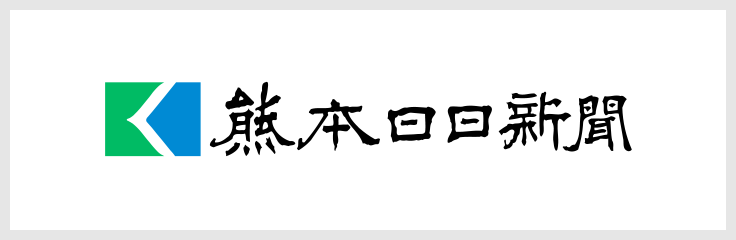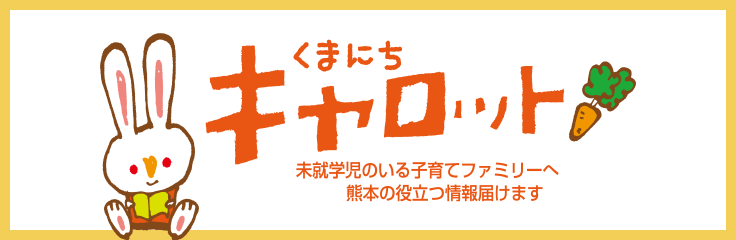貯蓄で重要なのは具体的な目標設定 収入減への対策や住宅問題も考慮に【知りたい!お金の話】

【今回のスタディー】独身者のライフプラン
近年、生涯独身の方が増えており、こども家庭庁の調べでは、2020年時点の生涯未婚率は男性28.25%、女性17.81%だそうです。「生涯未婚率」とは、50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合を指します。
一般的に会社員で独身といった場合、経済的に余裕があると思われますが、実際はそうでない人も少なくありません。原因の一つに、ライフプランにおける「目標設定の難しさ」があります。
貯蓄をする際に重要なのは、いつまでにいくらためると決め、そのためには毎月いくらためる必要があるかを決めることです。長期にわたる貯蓄計画が必要なライフプランは「教育資金」と「老後資金」ですが、独身の場合、教育資金がないため、具体的な目標が老後資金のみになってしまいます。そうすると、ゴールが遠すぎるが故に日々の節約意識が薄れ、思うように貯蓄が増えない場合があります。
統計局の「2024年家計調査」によると、単身者の1カ月あたり消費支出は60歳以上が15.9万円です。まずはこの金額の確保が一つの目安となるでしょう。もしこの金額を年金でカバーできるならば、それ以外の支出がどの程度かかるかを考え、貯蓄計画を立てましょう。
さて、収入源が自分一人の労働収入の場合、健康上の問題で働けなくなると生活に支障を来すことが考えられます。そうなったときの収入減少をどう補うか、それまでの貯蓄で補えなければ、別の収入源を増やすことも考えた方がよいでしょう。例えば、「就業不能保険」への加入や「金融資産」「不動産」といった資産の準備です。
最後に住宅の問題です。ずっと賃貸で暮らすのであれば、その分も老後資金に入れた上で、高齢になった場合でも住める場所を確保する必要があります。購入するなら、介護が必要になったときには施設に移住することも考え、住んでいる住宅を売却するか、貸し出すかについても考慮しておく必要があります。


「認知症」になった場合と「死亡後の事務処理」も…
本文で紹介した以外に準備しておきたいこととして、「認知症」になった場合と「死亡後の事務処理」があります。
前者の準備には「任意後見制度」があります。一人で決められるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにやってもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
後者の準備としては「死後事務委任契約」があります。亡くなった後の煩雑な事務処理を、生存中に誰かに委任するものです。委任者と受任者の間に正式な契約が取り交わされているため、法的な拘束力があり、確実に事務処理を実行してもらえます。
「家計簿チェック」の相談者を募集中!
専用フォームの必須事項にあなたの家計を入力するだけ。
講師に相談して、家計を見直してみませんか。採用分には図書カード3000円分進呈。