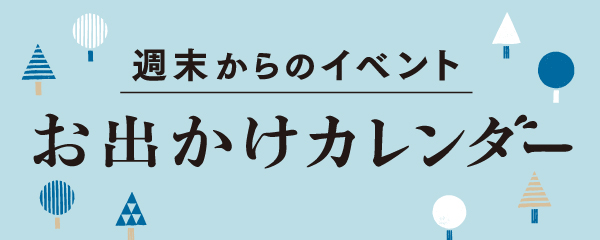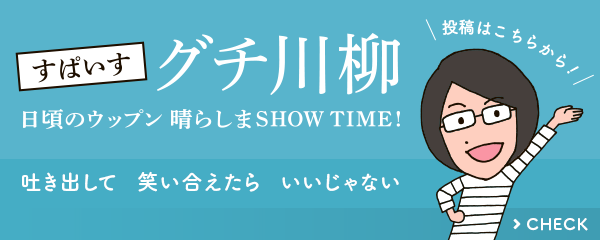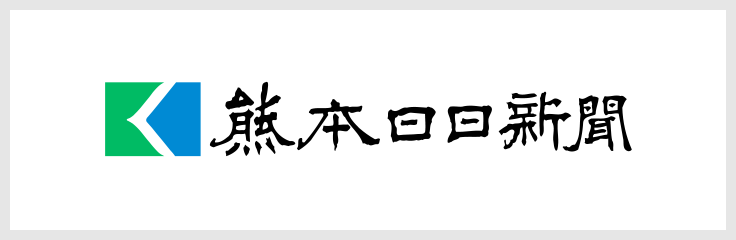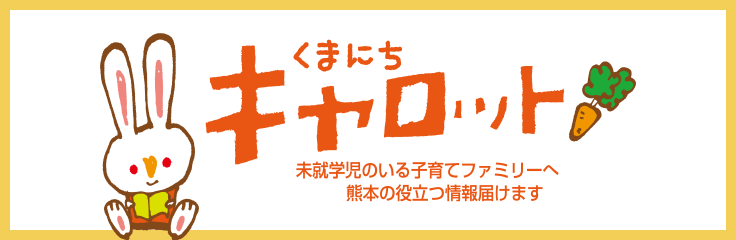台湾のお米ってどうなの?宜蘭県での米作りの現場に現地記者が潜入!【台湾ってこんなトコVol.18】

この記事を書いたのは


NNA台湾記者・山田愛実
アジアの経済情報を配信するNNAの台湾編集部員。台湾の屋台グルメが好きで、週末は市場や夜市によく出かけています。特に好きなのは豆腐を発酵させて作る「臭豆腐」。独特なにおいがしますが、意外と食べやすいので台湾に来たらぜひチャレンジしてみてください。
日本に輸出も…台湾北東部のお米の産地で聞きました
最近日本では、米不足を背景に海外産米の民間による輸入が増えています。中でも台湾産米の輸入量は米国産に次ぐ規模になっており、台湾産のお米は一部日本のスーパーでも見られるようになりました。読者の皆さんも、台湾のお米を目にする機会があるかもしれません。
そこで今回は、台湾のお米がどのように消費者に届けられているのか、日本にも輸出した実績がある台湾北東部のお米の産地、宜蘭県五結郷で米作りに関わる人たちに話を聞いてきました。


お米の名産地・宜蘭県五結郷ってどんな所?
宜蘭県五結郷は台北市から車で約1時間。
蘭陽平原東南の太平洋に面した場所に位置し、宜蘭県で最も主要な河川である蘭陽渓の河口があります。雪山山脈を水源に持つ蘭陽渓などの良質な水資源が、おいしいお米を育んでいるのだそう。水稲栽培面積は約1,100ヘクタールで、コシヒカリ(越光米)も生産されています。
ちなみに蘭陽渓の上流にある三星郷はネギの名産地として知られ、人気ドラマ「孤独のグルメ」でも紹介されました。


コシヒカリの収穫作業を見学
実際にお米を作っている人を見てみたい!ということで、コシヒカリを生産する方福在さん一家の収穫作業を見学させてもらいました。
この日の宜蘭の最高気温は34度。まぶしい日差しが照りつける中、一家総出で稲の収穫作業を行っていました。


夫の方福在さんがコンバインを操作し、妻の游麗雪さんや息子の方子軒さんがコンバインを誘導しながら田の縁にある稲を手作業で刈り取っていました。
游さんによると、収穫作業は6月中旬から始まっており、品種によっては9月中旬ごろに終わる見込みだといいます。
台湾では最も暑い時期。立って話を聞くだけで汗が滝のように流れ、へばってしまいそうになってきたこちらとしては頭が下がる思いになりました。


息子の方子軒さんは26歳。大学時代は電子分野を専攻していたそうですが、両親を支えるため卒業後にコメ作りの道に進んだといいます。収穫期の今は毎朝6時半ごろから夜7時まで稲の状態をみて収穫に追われているそうで、「暑いのがとにかくつらいけど、父が提案を聞き入れてくれるからやりがいがある」と話してくれました。 提案というのは、農薬散布用のドローンの導入。これまで3ヘクタールの散布に1日かかっていたのが、1日で10ヘクタール以上にも対応できるようになったといいます。こうした効率の改善も家族経営のため取り入れやすく、不満につながらないのだとか。オフシーズンには2カ月ほど休めるのも魅力だと教えてくれました。




五結郷農会に聞く 安全・安心の米作りのためのルール
五結郷農会(農協に相当)で五結郷のお米について話を聞くことにしました。「宜蘭県の米作りは日本と同じように収穫が年1回だけの『一期作』。味も安全性も日本に引けを取りません」。そう自信たっぷりに語るのは、五結郷農会(農協に相当)の游偉榛総幹事です。


台湾では農薬使用に厳しい規制が設けられています。游さんによると五結郷農会では天気予報から今後どのような病気や害虫が発生するかを予想し、予防的に農薬を使用したり、地域一帯で病気や虫害の防除を徹底したりすることで、農薬の使用を必要最小限にとどめています。こうした取り組みの結果、有機栽培に移行できた農家もあるそう。
また同農会では、生産者が特定できるトレーサビリティー(追跡可能性)制度を導入し、生産者に安全性への意識を徹底しているといいます。
五結郷農会は2020年に1,600トンの政府備蓄用米を日本に輸出した実績を持ち、いまも輸出を検討する業者からの問い合わせが相次いでいるそうです。
游さんは、宜蘭県産のお米は「清らかさ」「香りと食感」「安全性」「風味」を兼ね備えたお米として台湾でも高い評価を集めているとして、「日本の方たちにも安心して食べていただけます」と自信をのぞかせていました。


収穫されたもみは工場で乾燥
収穫された稲がどのように消費者のもとへ届けられているのか、五結郷農会が管理する孝威村の精米工場に見学に行きました。
精米工場を訪れると、収穫されたばかりのもみを満載したトラックがちょうど到着しました。まずは乾燥機にかけるため、もみを一部採取して水分量を測定します。日本では農家が自分たちで玄米にする場合もありますが、台湾ではこのようにもみの状態で工場に集められるのが一般的です。




水分量の測定が終わったら、もみの荷下ろしを行います。大量のもみが「ザザーッ」と気持ちのいい音とともに流れ落ちていく様子は壮観です。運び込まれたもみはすぐに乾燥機にかけた後に倉庫に保管され、注文が入ってから精米し出荷されるそうです。
もみの状態で工場に集められることを除けば、栽培方法や精米、安全管理は日本とほぼ変わらないということが分かりました。






五結郷農会は、五結郷に加え周辺の羅東鎮、蘇澳鎮、冬山郷などから毎年1万2,000トンのもみを受け入れ、6,000トンは政府備蓄用の「公糧」として保管し、残りの6,000トンを販売用として台湾北部一帯の飲食店や学校給食用、スーパーなどに供給しています。台湾を訪れた旅行者も、飲食店で口にする機会があるかもしれませんね。




宜蘭産の有機コシヒカリを食べてみました
五結郷で作られた有機栽培のコシヒカリ「夢田越光米」を実際に食べてみることにしました。筆者は普段から台湾のお米を食べていて特に不満はないのですが、一体どう違うのか確認してみようと思います。


お米を開封したらびっくり。ミルキーな甘い香りがほんのり漂ってきました。いつものお米とはこの時点で全く違います。炊いている時も炊きあがりもとてもいい香りです。
そして炊きたてのお米を食べてみると、さらに驚き! お米の一粒一粒がしっかり立っていながら、柔らかく粘りがあり、かむと優しい甘味が口いっぱいに広がって幸せな気分になりました。しょうゆ味の和のおかずにも、台湾の甘味の強いおかずにもどちらにもぴったりだと感じます。
普段あまりお米の産地や銘柄にこだわっていませんでしたが、これからは少し気にしてみようかなと思える経験でした。今後は宜蘭産をはじめ、台湾各地の色んなお米を試してみようと思います。


いかがでしたでしょうか。
台湾でお米作りに関わる人たちの声を通じて、台湾のお米を少しでも身近に感じていただければ幸いです。
日本のスーパーで台湾のお米を見かけた際や、台湾に旅行に来られる際にも産地や銘柄をぜひチェックしてみてください。新しい発見があるかもしれません。