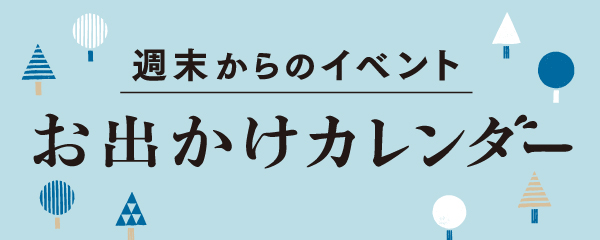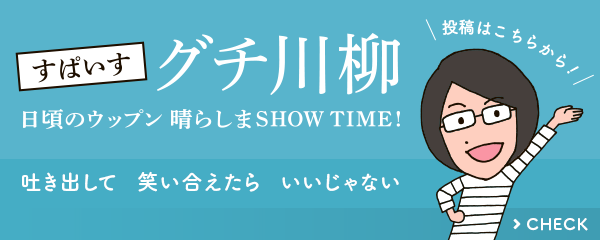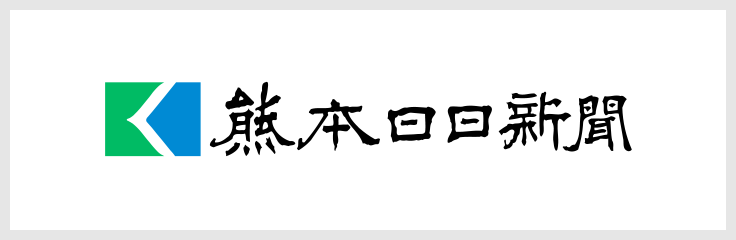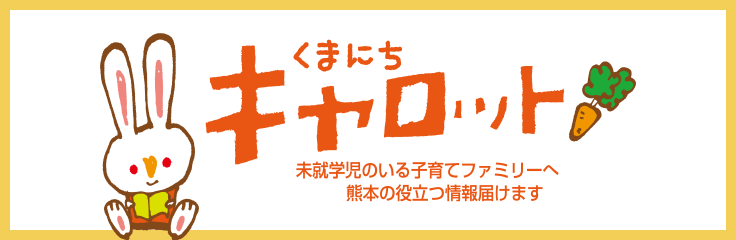【青木由香の台湾吃吃メモ14】「電鍋」に生かされる台湾人たち



青木由香さん
神奈川県生まれ台湾在住。執筆や取材・旅行のコーディネートを通して大好きな台湾を紹介。雑貨店「你好我好(ニーハオウォーハオ)」(台北市)店主。
目次
もはや“国鍋”!? 日本生まれの旧式炊飯器
「電鍋(デェングォー)」は国花や国鳥に匹敵する、もはや台湾の“国鍋”。
一家に1.7台あると言われる、元は日本生まれの旧式電気炊飯器です。
当然、日本ではもう生産されていません。




外釜に入れた水が沸騰して内釜の食材を湯煎調理し、水がなくなれば自動でスイッチオフ。
放置しても空だきの心配がない蒸し器のような物だから、蒸し調理が多い台湾では炊飯以外で大活躍します。




柔らかくなって、包丁が入りやすい。
例えば、鶏のスープ。
電鍋なら食材が100度の蒸気に包まれ、緩やかに温度が上がるので直火のようにボコボコ煮立たず、あくも出ない。
うま味をじっくり引き出した、プリップリな鶏肉の澄んだスープができます。


肉まんなど、料理の温め直しも蒸気でふっくら。
電子レンジより温かさが長持ち。


簡単な調理をしたり、お弁当を温めたりするために置いてある。
近所の雑貨屋さんにて


豚の角煮も、膨張した空気が冷めて収縮するまで蓋を開けなければ、圧がかかりギュッと味が染み込みます。
万能ゆえに嫁入りや一人暮らしの必需品。
オフィスや食堂、屋台、コンビニと街を歩けばやたらと目に入る。
台湾に来たら、台湾人がどれだけ電鍋に生かされているのか実感できますよ。








あわせて読みたい




【青木由香の台湾吃吃メモ13】心とろける豆花は食感も味わいも千差万別
「吃吃(チーチー)」とは、台湾の人がよく口にする「ほら、遠慮せず食べて!」的な言葉。食べることが大好きな青木由香さんがつづる、いつかの台湾旅に役立つかもしれ…